「自分が面白いと思うもの」突き詰め視聴者の心を掴む ―HTB「水曜どうでしょう」ディレクター・藤村忠寿さん 【北大人に聞く 第10回】
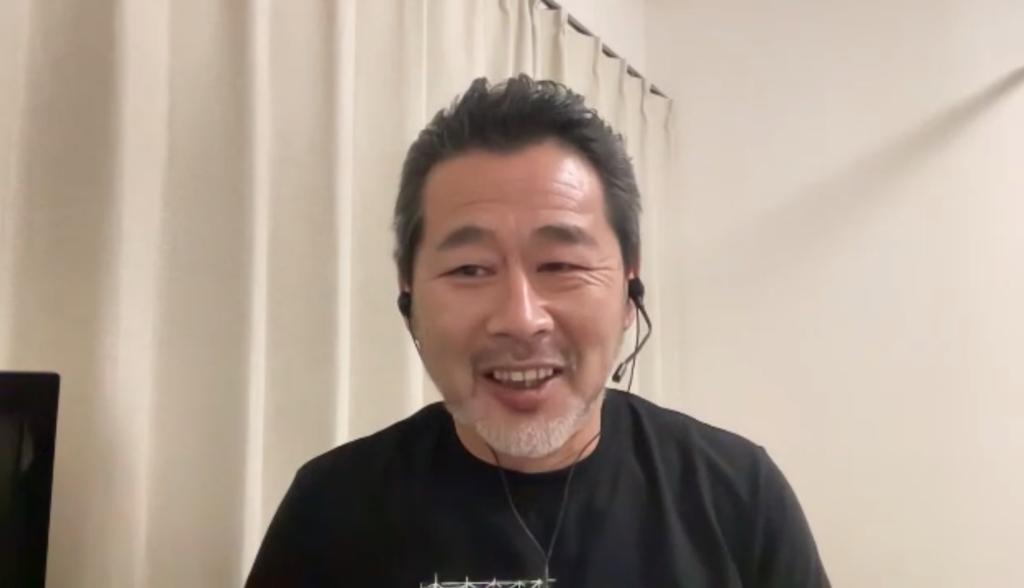
ローカル発のバラエティ番組としては異例のヒットを記録した北海道テレビ放送(HTB)制作の「水曜どうでしょう」。「北大人に聞く」第10回では同番組チーフディレクターで本学法学部卒業生の藤村忠寿(ただひさ)さんにこれまでの歩みや番組作りへの思いなどを聞いた。
北大生としての自由な生活の中にあった原風景
「水曜どうでしょう」はHTBで1996年から02年までレギュラー放送され、その後は不定期で新作が制作されている。鈴井貴之さん・大泉洋さんらが2人のディレクターとともに国内外で珍道中を繰り広げる独特のスタイルが視聴者に受け、レギュラー放送終了後もなお根強い人気を誇る。現在に至るまで同局や全国各地で再放送され続け、番組DVD・ブルーレイの出荷本数は21年までに累計500万枚を突破した。そんな大ヒット番組の原風景は、80年代の北海道にあったという。
藤村さんは愛知県名古屋市出身。北の大地への憧れから本学を志望し、1年間の浪人を経て85年に入学した。当初は政治家に関心があり行政法などを学ぼうと法学部に進学したものの、部活動のラグビー漬けの生活を送ることに。「学生としてはダメだった」と当時を振り返る。
「自由」やフロンティア精神に憧れて全国各地から学生が集まる本学には当時から「学力だけではない魅力」があった。学びを突き詰める学生がいる一方、学業以外にも存分に手を伸ばせる環境で藤村さんの「心が開かれた」という。
「番組を見たラグビー部の同窓生には『学生時代と同じことをやっているじゃないか』と言われる」。後に「どうでしょう」で定着した出演者とディレクターの4人で車に乗って移動するスタイルは、学生時代の仲間内での旅の経験がベースになっていると話す。冗談を言い合ったり、仮装をしたり、バイクで旅をしたり…。番組内のそうした1コマも学生時代の経験から生まれた。
「目的地は必ずしも重要ではなく、ワイワイ話しながら自由なフィールドで遊ぶ。そんな『無駄な時間』を過ごすことが楽しかった」。
報道志望で入社、行き着いたのは遅咲きの「どうでしょう」
藤村さんがテレビの世界を志したのは本学在学中のアルバイトがきっかけだった。先輩の誘いを受け、HTBでニュース取材の助手として働いていた。数々の現場を目の当たりにする中で野次馬根性も味方して「これは仕事として楽しそう」と思い至ったという。
報道の現場で働くことを希望していたが、入社後に配属されたのは東京支社の業務部。デスクで数字を追いかける日々が続いた。希望の部署への配属とはならない中でも「仕事=お金のため」と割り切り、仕事と遊びを分けて考え乗り越えた。
東京で5年間働いたのち、札幌の本社に異動が決まる。しかし配属されたのは制作部だった。「モザイクな夜」でディレクターを務め、1年後に番組は打ち切りに。ディレクターとしては1年少々の経験で嬉野(うれしの)雅道さんとともに自分の番組を任され、そこで産声を上げたのが「どうでしょう」だった。前番組から関わりのあった鈴井さんに加えて、演劇の活動をしていた大学生の大泉さんの面白さに注目してキャストが揃う。
番組作りで最も重視したことは「自分が一番面白いと思うものは何か?」への問いかけだったという。元々テレビは好きで「笑いを嗅ぎ分ける能力に自信はあった」。「電波少年」や「気分は上々」などの旅番組からも着想を得つつ、学生時代の旅の経験も振り返り「旅の途中のハプニングが面白い」と思い至る。1回のロケでの撮影量や明確な目的を前もって設定することは特にせず、「道中どれだけ楽しいか」に集中。「100キロメートルの間、誰もしゃべらないと不安になるがそれが面白い。そういう客観的な目線も忘れなかった」。そうして自然発生的に生まれた会話の数々が、視聴者を画面に釘付けにしていった。初回から視聴率は好調で「やっぱり面白いんだな」と手応えを感じていた。
しかし「他のこともやりたくなった」と番組は6年間でレギュラー放送の幕を下ろし、番組を再編集しDVD化することに。全国的に話題を呼んだのはDVDの発売後だった。「北海道ローカルで結果は出ていたのでヒットは当然のことと手応えはあったが、それでも遅いなと思った」。ただしDVD化やグッズ製作は戦略ではなく「興味があったから」取り組んだものだった。「結局は自分がやりたいかどうか」。
今後については「水曜どうでしょうをやめる理由はない。面白いか否かを超越してしまっており、自分たちの人生を見せる番組になっている」とした上で「次の世代に託すということもないだろう」と語る。近年はテレビマンの枠にとらわれず活動の幅を広げ、自ら演劇の舞台にも立つ。芝居に興味を持ち「生で演じることが楽しくなった」。将来的には映画制作にも取り組みたいと意欲を見せる。

バラエティ番組にこそ知性が必要
そんな藤村さんは「本当にヒットする番組は制作者の熱意で作ったものなのではないか」と投げかける。情報が無数に溢れる現代、旅が目的にとらわれがちなのと同様に、セオリーや数字ばかりに依拠して番組を作っても「これ仕込みじゃん」と思われてしまう。
その上で報道番組だけでなく「バラエティこそ知性を感じる番組でないといけない。(多少荒々しくとも)知性を伴ってやり切ることも必要」と力説する。「テレビは社会を映すもの。テレビが知性を失うということは、社会が知性を失うということなのではないか。社会全体に思想がなく、流されるままになってしまう」。コンプライアンス(法令遵守)で身動きが取りにくい現代の社会に対しても一石を投じる。「人々の生活がコンプライアンスでがんじがらめになってしまっている。人間として生きる方向をちょっと考え直して、もっと自由に、多様性を認められる寛容な社会になればいい」。
ローカル番組については「外から来た人がインターネットを通じて発信する時代になっており、地域を限定することは情報の縛り付けなのではないか」と指摘。一方で「ローカル局がやるべきことは地域のジャーナリズムの追求」とローカルメディアに期待される役割も健在だと語る。
社会のせいにせず、自分たちで変えていくという意識を
学生に向けては新型コロナウイルス禍を踏まえ「閉塞感を自分たちで変えていくという意識を持ってほしい」と投げかける。「コロナ禍は仕方がないことだが、『やっぱりこれはおかしい』ということも分かってくると思う。飲み込まれることなく、誰かが打ち破らないといけない。社会のせいにするのは間違い」と力を込める。藤村さんがコロナ禍を生きる大学生ならば「この状況を逆手に取り、しばらく大学に行けないのはラッキーだと思って各地を1人で旅して回るかもしれない」とユーモアを交えて語った。
テレビ業界をはじめクリエイティブなことに関心を持つ学生に対しては「今は個人の発信の時代であり、選択肢に王道はない。考え方や実力次第だ」と話す。「自分が何を考え、何を発信できるのか考えてほしい。個人の力が試されている」。

<プロフィール> ふじむら・ただひさ 愛知県名古屋市出身。1990年3月に本学法学部卒業、北海道テレビ放送(HTB)入社。東京支社での勤務を経て、96年から02年まで同局でレギュラー放送されたバラエティ番組「水曜どうでしょう」のチーフディレクターを務める。現在は同局エグゼクティブ・ディレクター。
